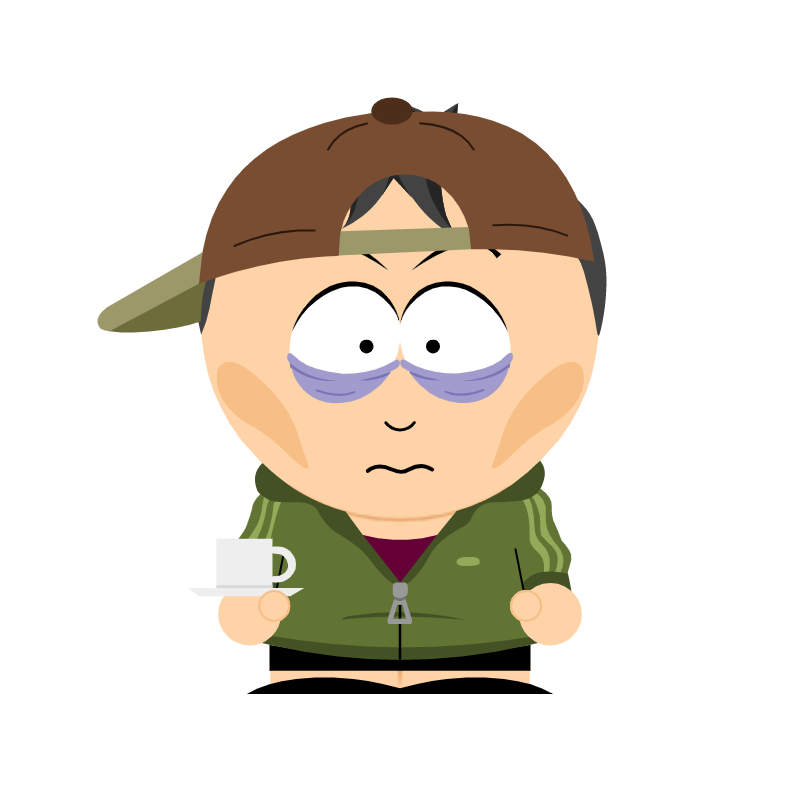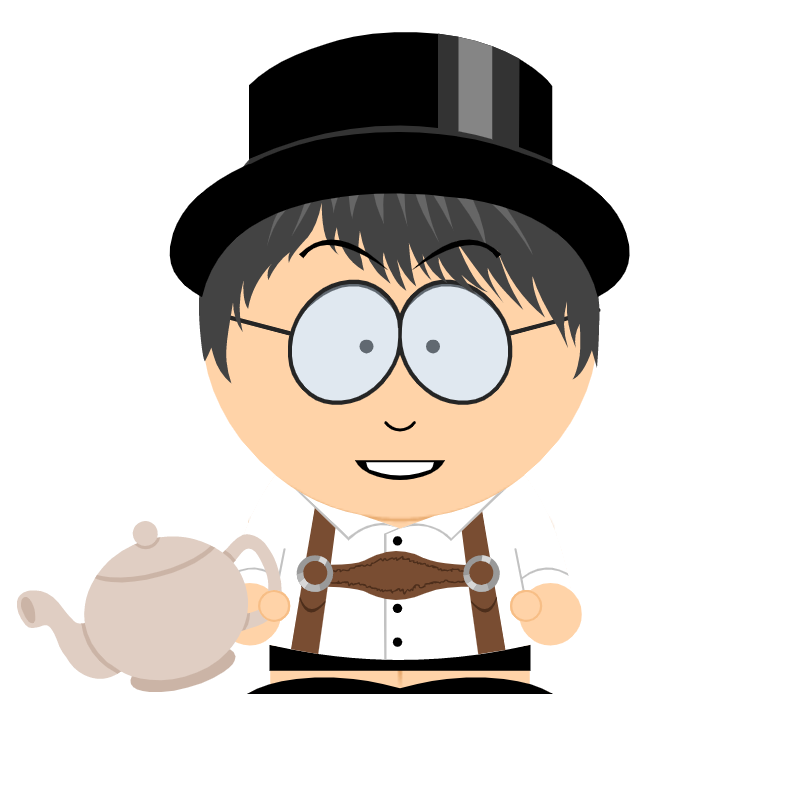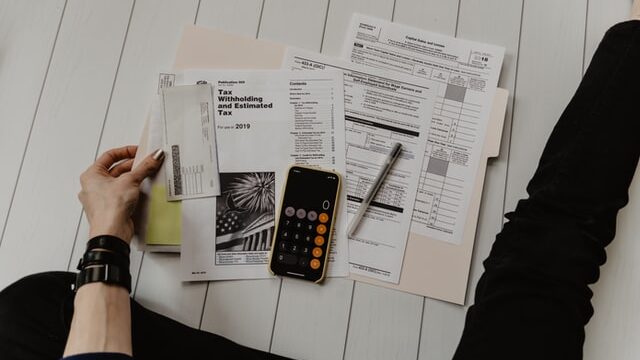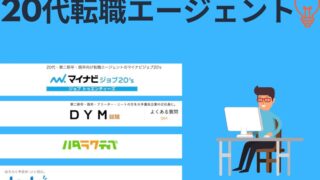ぼくはこれまでに転職5回以上しているのでその都度引き継ぎ書を作成してきました。
結論から言うと「引き継ぎ書がなければ自分で作ってしまう」
なぜなら、引き継ぎ書を作成することで仕事の流れや不明点が明確になって仕事効率が上がるからです。
そこで今回は退職するときには必要になる引き継ぎ書について書き方からメリット・デメリットまで解説していきます。
引き継ぎ書とは?今の仕事のやり方をわかりやすい方法で書いた説明書
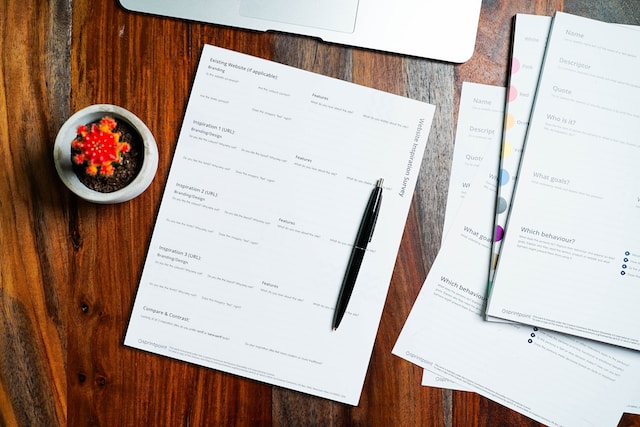
結論から言うと自分の仕事内容を後任者に引き継ぐ為の資料です。
「さすがに誰でも知ってるよ」という声が聞こえてきそうですがいざ「引き継ぎ書を作成して」と言われたら手が止まる人が多いんですよね。
しかも出来上がった引き継ぎ書がA4の紙1枚みたいなことがありました。
- 引き継ぎ書は自由に書くのはNG
- 引き継ぎ書は初心者に向けて書くこと
引き継ぎ書は自由に書くのはNG
会社に引き継ぎ書のフォーマットがあれはそれ通りに作成すれば良いのですが無い場合に自由に作る人がいます。
自由に作っても良いのですがだいたい意味不明な引き継ぎ書が出来上がります。
「Aの項目は社内?社外?」
「Bのやり方は他の人はしてないらしいけど大丈夫?」
上記のようなことが発生します。
書類作成が上手な方なら普通に出来上がりますが下手な方に自由に作られたら大変です。
引き継ぎ書は初心者向けに書くイメージ
後任者があなたとほぼ同じ仕事内容かつ同じフロアで仕事していたならある程度ポイントだけ記載してもOKです。
しかし例えば後任者が同じ営業職をしていても扱っている物が違ったり訪問するお客様の業種が違うとほぼ素人レベル。
その為、引き継ぎ書を作成するときは僕は必ず初心者の後任者だと思って作成するようにしてます。
そうすることで「主語がないと何のことか分からなくなるなぁ」という気づきがうまれます。
引き継ぎ書がないときの書き方 記載する7項目

引き継ぎ書には情報満載であることに越したことはないのですがあまり入れすぎてもどこから見たらいいのか分からなくなります。
僕が引き継ぎ書を作成する時に最低限入れている項目を紹介します。
- 仕事の概要
- 業務の流れ
- 仕事相手の情報
- 業務の進行状況
- 業務上の注意点
- データ、資料保管場所
- 業務上必要な連絡先
①仕事の概要
自分のやっている仕事概要を入れるようにしています。
僕は営業職が長かったので下記の様な感じです。
| 担当エリア | 〇〇県〇〇市 |
|---|---|
| 担当年数 | 〇〇年 20××年〜 |
| 担当数 | Aが20軒 Bが30軒 |
| 売上高 | 月間〇〇万 年間〇〇万 |
実際はもう少し盛込みますがだいたいこんな感じです。
②業務の流れ
業務の流れを記載します。業務の流れは職種によってかなり違うと思いますが職場独自ルールも入れることができるので後任者には助かります。
1日の流れ
- 朝8時30分に出社 (職場ルールは9時)
- 内勤 10時まで (11時までの内勤OK)
- 昼 14時に一次帰社 (上司報告必要)
- 夜 直帰 (直帰は連絡なし自由)
1ヶ月の流れ
- 毎週月曜日朝からミーティング
- 月1回の会議は第2週の火曜
- 第3週は研修
ざっくりと上記のような期間ごとに分けて業務の流れを記載してました。
③仕事相手の情報
僕は営業職だったので担当顧客情報を記載していました。
営業職ではない場合は必要ないかもしれません。
- 顧客の基本情報
- 訪問ルール
- 顧客訪問の注意点
自分の知っている情報で後任者に必要な情報をExcelシートに詰め込みました。
④業務の進行状況
自分のエリアだけのイベント企画を予定していたり職場全体のイベントなどがある場合は記載します。
営業計画と現在までの数字などを一覧表にしてデータを出して進行状況を分かりやすくしてました。
⑤業務上の注意点
業務全体の注意点を記載します。
この注意点は引き継ぎ書の中でも後任者にとってかなりありがたい情報です。
- 〇〇月になるとA製品が大量に出るので事前に準備必要
- B製品のクレームが多いエリアでトラブル起きたら〇〇さんに相談
⑥データ、資料保管場所
業務に関するデータや資料は引き継ぎ書と一緒に渡すと大量になって困ります。
日頃から使う様なデータや資料は職場のサーバーのどこに保管してあるかを記載します。
⑦業務上必要な連絡先
業務上で電話やメールをしないといけないので連絡先一覧表を付けます。
引き継ぎ書をわかりやすく作成するメリット・デメリット

引き継ぎ書を作成すると作成側に取ってメリット・デメリットがあります。
- メリット
- デメリット
メリット
- 対面引き継ぎが楽になる
- 退職日前に堂々と有給休暇を消化できる
- 自分の仕事を振り返ることができる
①対面引き継ぎが楽になる
後任者に最初引き継ぎ書を渡しておくと対面説明がかなり楽です。
後任者が分からないことだけ質問してきて終わり。
後任者が聞き忘れていても引き継ぎ書みたら一目瞭然なので無駄な連絡なくなります。
②退職日前に堂々と有給休暇を消化できる
退職日まで引き継ぎが間に合わなくて有給休暇使えないという話があります。
しかし引き継ぎ書を作成しておけば堂々と有給休暇消化しやすくなります。後任者が引き継ぎ書見て分からなくても上司や同僚に引き継ぎ書渡して聞けば100%解決。
③引き継ぎ書を作りながら自分の仕事を振り返れる
引き継ぎ書を作ると自分のこれまでの仕事を振り返れます。
「自分のこの部分は弱いなぁ」
「これはこれを試しておけばもっと良かったかも」
上記のように振り返ることで転職先の仕事に活かすことができますよ。
デメリット
- 作成手間がかかる
- 後任者が見ない
①作成手間がかかる
退職が決まっていて他にも残務処理があるのにしっかりとした引き継ぎ書を作成するとなると大変です。
業務終わりに自宅で作成しないといけなくなることも。
②引き継ぎ書を作成したのに後任者が見ない
せっかくしっかりとした引き継ぎ書を作成したのに後任者があまり見ずに質問をしてくることがあります。
ベテラン社員にありがちなのですが見るより聞いた方が楽だということ。
そうなると引き継ぎ書の作り損ですね。
【体験談】引き継ぎ書がないよりわかりやすく作成して良かった話
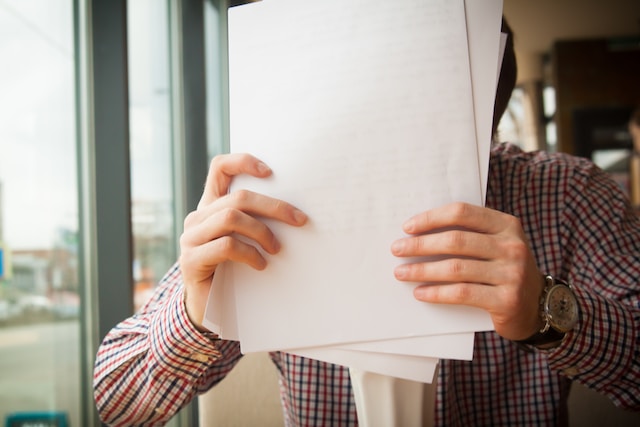
これまで退職する度に引き継ぎ書を作成してきましたが良い思い出しかありません。
- 退職を上司に伝えるときが楽
- 退職日前に有給きゅうが取りやすい
- 上司や同僚からの評価が上がる
①退職を上司に伝える時が楽
退職を伝える時に引き継ぎ書も一緒に持参するようにしています。
辞める決意の現れにもなり上司もしつこい引き止めすることなくスムーズに話が進みました。
②退職日前に有給休暇取りやすい
退職日前に有給休暇を上司に伝えても引き継ぎ書作成しているとすんなりOKくれました。
後任者はすぐに決まらないことは多いですが引き継ぎ書さえあれば僕が辞めた後も上司は引き継ぎ書を後任者に渡せば良いだけなんで楽ですからね。
③引き継ぎ書をしっかり作ると上司、同僚からの評価上がる
最後に自分の評価が上がっても意味はないかもしれませが気分は悪くありませんね。
「すごい引き継ぎ書作成してしっかり仕事してくれてたんだなぁ」
「さすが最後まできちんとしてますね」
上記のような言葉をかけられたことがあります。
④引き継ぎ書がない!という場合は後任者はどうしたらいいですか?
引き継ぎ書は退職した時にだけ必要というわけではありません。
部署異動や転勤でも必要になります。
また1番のメリットは今の仕事をしながら引き継ぎ書を並行して作ることで今の仕事の改善点が明確になることも。
もし前任者が引き継ぎ書を作っていかなかったら諦めて自分で一から引き継ぎ書(業務マニュアル)を上司や同僚から情報を得て作りましょう。
引き継ぎ書がなくても自分のためにもわかりやすい引き継ぎ書を作ろう
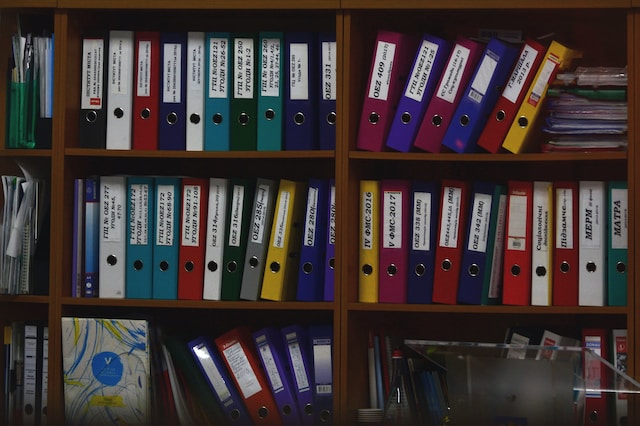
引き継ぎ書を作成するのは確かにめんどくさいです。しかも退職する場合はなおさらですね。
しかしデメリットばかりではなく間違いなくあなたの成長に繋がるのも間違いありません。
「精神的に病んでる」や「どうしても今の職場の為なんかに作成したくない」という状況ではない限り作成をおすすめします。


※本記事の内容は「転職CAFE」と提携するサービスのPR情報が一部含まれています。提携企業様はこちら。
※PR情報から商品の申し込みをいただいた際は、各広告主から一部報酬を頂くことがあります。しかし、報酬が各紹介サービスのレビューやランキングに影響することは一切ありません。レビュープロセスと評価項目をもとに透明性を遵守し紹介しています。
※企業様から頂いた報酬は、皆様(読者様)にとってより役立つコンテンツの充実・更新、品質を担保するための独自調査費(アンケート調査やインタビュー調査)することに充てています。
※コンテンツに関する問い合わせはこちらから。